
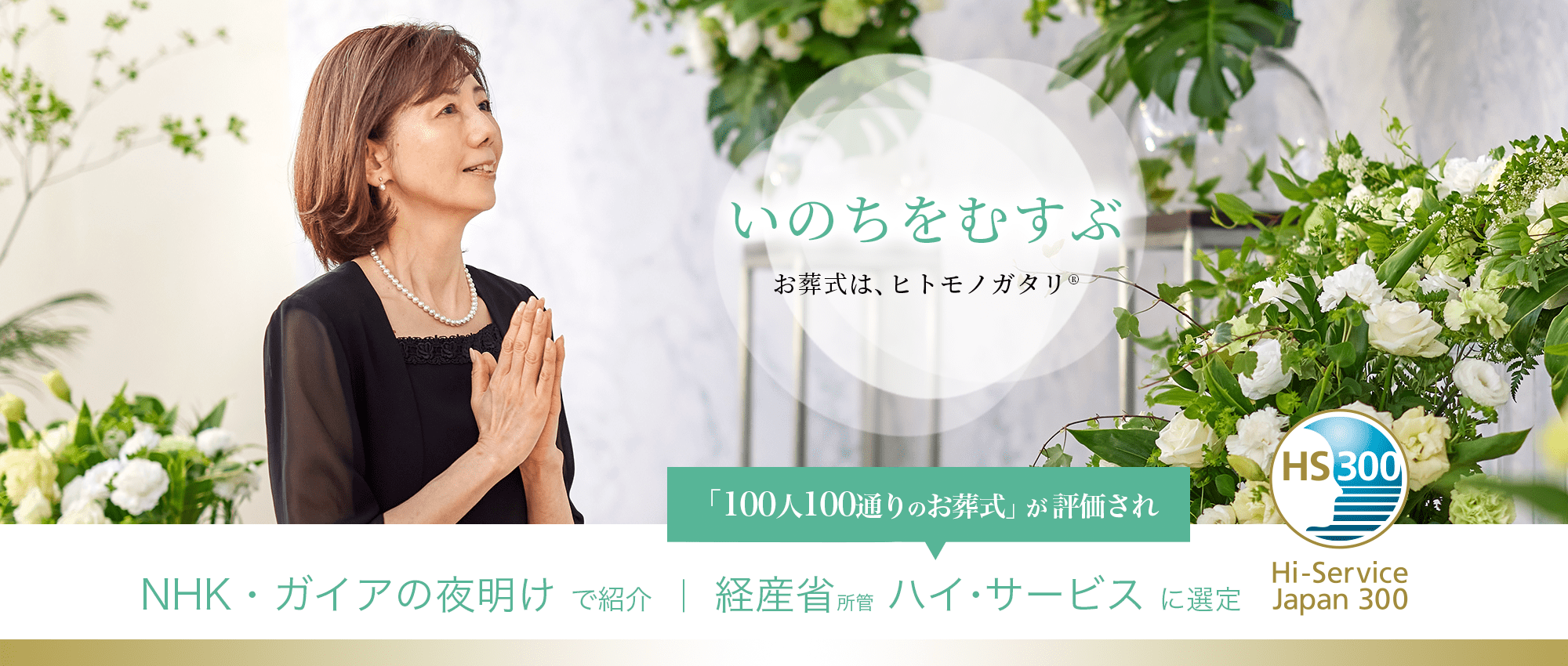
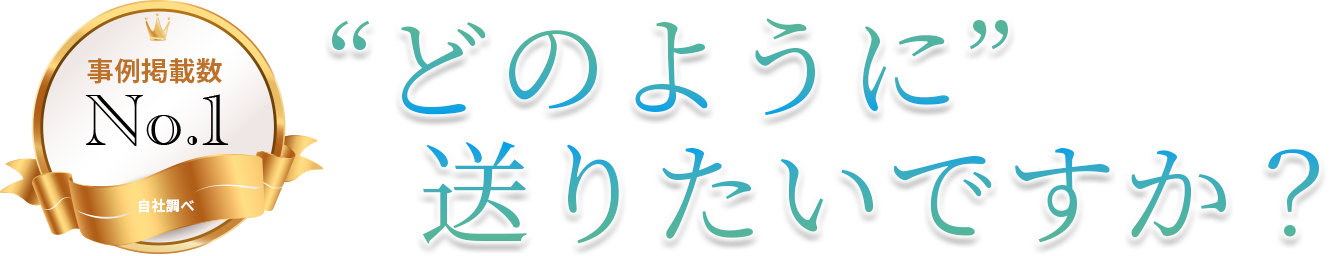


費用について
送り方によってご葬儀の費用も変わります。ご家族様ごとにお話を伺い、基本セットをベースに
過不足のない納得のお見積りをご提案いたします。
プランの一例
-

一日家族葬
スタンダード1日でご葬儀と告別式を行い、少人数で3密を避けた会葬者さまのご負担が軽いプランです。
10名程度
- お迎え
- ご安置
- 告別式
- 火葬
10名
程度588,500
円
-

二日家族葬
スタンダードご家族だけでゆっくりお別れを。一般の会葬者をお招きせず、家族や親しい友人だけで送る人気のプランです。
10名程度
- お迎え
- ご安置
- 通夜
- 告別式
- 火葬
10名
程度791,340
円
-

火葬式
スタンダード費用を抑えてシンプルなお見送りを。お通夜・告別式などの儀式を行わず、限られた親しい方のみで行うプランです。
5名程度
- お迎え
- ご安置
- 火葬
5名
程度209,000
円
-

一般葬
スタンダードお世話になった方々をお招きしてお別れの時間を。故人と生前に付き合いのあった人との縁を大切にしたプランです。
60名程度
- お迎え
- ご安置
- 通夜
- 告別式
- 火葬
60名
程度1,107,810
円
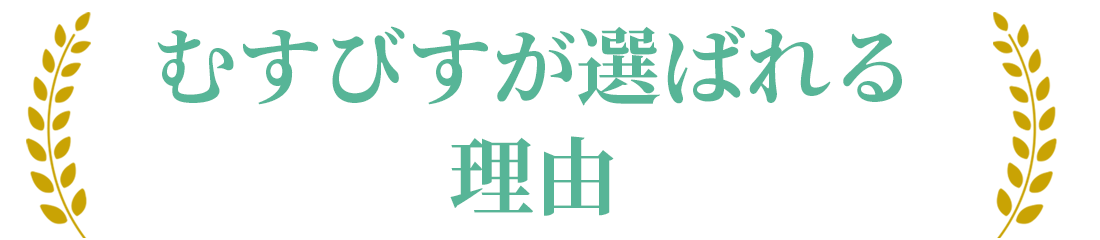
料金・サービス・お葬式の送り方など、むすびす独自の取り組みが評価され、お客様から多くの声を頂戴しました。
項目ごとにご紹介いたします。


お客様の声
-
料金・プランについて
-
対応について
-
送り方について
-
葬儀前後のサポートについて
ご葬儀の「わからない」「不安」、
でも「大切な人をちゃんと送りたい」
そんなお悩みを解消する、
むすびすの取り組みをご紹介いたします。

資料請求・ご相談はこちらから
既に他の葬儀社で御遺体を搬送されたあとでもご依頼可能です。
大切な方との最期のお別れは、信頼できる葬儀社をお選びください。
-
24時間365日。専門のスタッフが対応します。
0120-74-9072
どんなことでもお気軽にご相談ください。
お客様から届いたお喜びの声
実際にむすびすのお葬式で葬儀を行ったお客さまから寄せられた声をご紹介いたします。
-

故人にできることがあって嬉しかった
埼玉県比企郡川島町 H様
- 家家族葬
- 仏仏教
- 中30 - 50名
- 蓮馨寺講堂
今回の葬儀を通して、葬儀に対するイメージが大きく変わりました。遺体を見ることの恐怖は、エンバーミングや着せ替えによって無くなり、献紅茶をすることで、亡くなった人に対してできることがあると、嬉しい気持ちになったからです。本当に感謝しかありません。今回の葬儀でお世話になり、全てにおいてお任せできることがわかったので、知り合いに勧めました。
-

ストレスなく想像以上の葬儀ができた
埼玉県北本市 Y様
- 家家族葬
- 無無宗教
- 小10 - 20名
- 県央みずほ斎場
問い合わせ時から葬儀終了まで、担当の皆様がとても気持ちよく対応していただき、何のストレスもなく思っていた以上の葬儀が出来たことから、知り合いにすすめられます。どのスタッフからも会社の社員教育のすばらしさを感じました。本当にむすびすさんにして良かったと、家族一同感謝しております。大変お世話になりました。ありがとうございます。





































